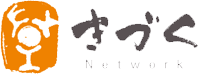NEWSお知らせ

自社に合わせた失敗しないメンター制度
メンター制度を導入する組織が増えてきた背景として、社会環境の変化があります。
以前は、組織の中で自然に成長していく環境がありました。しかし、世の中の変化スピードの速さ、人材が不足する中での生産性・効率・業績追及によるプレイングマネジャーの増加といった状況から、部下や後輩にじっくり目配りをして育成をする、という環境ではなくなってきました。

また、仕事で使う機器の発達や環境の変化に目を向けると、個人の仕事が外からは分かりづらくなったということも一因としてあります。(携帯、メールでのやり取りなどによるブラックボックス化)ひと昔前のように、先輩社員が電話で話している内容を聞いて真似をする、覚える、といったことや文章の書き方を真似をする、といったことがしづらくなっており、見て盗む、仕事ぶりを見て自然に学ぶ、ということも難しくなっています。
更には、ハラスメントという言葉の定着により上司、先輩が部下、後輩に対するコミュニケーションに対して不安を抱いていること、自ら積極的にコミュニケーションを図る若い世代がいないこと、更には、女性活躍推進やワークライフバランスといった国策の関係で、今まで育成対象となってこなかった人材に光をあて、成長してもらう、といった様々な状況が相まって、注目されてきたのがメンター制度です。
意図的に「支援」「育成」という関係性をつくることで、個人、組織の成長につなげようという機運が高まっていると言えます。
2.メンターとは

■メンターとは:
仕事や生活、人生において個人の“手本”となり、 指導・支援を行う人のことをいいます。知識やスキル、経験の豊かな人(メンター)が、まだ未熟な人(メンティ)に対して、目標達成や成果向上、成長のために仕事のやり方や人間関係の築き方、課題解決、意欲促進、モチベーション向上など様々な場面で、キャリア形成や心理・社会的な側面など総合的な支援を継続的に行います。
単なる話を聴く相談役ではなく、業務・実務ではないもっと大きなところでの目指す姿を明確にし、サポートを行うことでメンティに自律性や自信を持たせ、メンティ自身が前向きに仕事生活、社会生活を送る支援を行う役割を担います。
■メンターの語源:
ギリシア神話の登場人物『メントール』の名前に由来します。オデュッセウス王がトロイア戦争に出陣する際、自分の息子テレマコスの育成をメントール(Mentor)という人物に託しました。 託されたメントールは帝王学や学問のみならず、人としての成長も含め全人格的な育成・指導を行いテレマコスを王の期待以上に大きく成長させたことから、全方位的に指導支援を行う人のことをメンターと呼ぶことになりました。
3.メンター制度とは

■企業制度としてのメンター制度:
企業や組織が制度として導入する場合は、離職防止、モチベーション向上、女性活躍推進、新規事業促進、管理職登用トレーニングなど様々な目的で実施されています。
また、「斜めの関係」と言われ、同じ社内であっても異なる部門の上司や先輩が設定されるのが通常です。それは、評価や日常の仕事に直接的な影響がない分、本音で相談しやすくメンター側も固定概念やバイアスを持たず客観的かつ適切なアドバイス、支援が可能となるためです。
■メンター制度の期待効果:
【組織】
メンター、メンティがともに成長すること、社内のコミュニケーションが活発になり現状把握が常に行われるため組織が活性化されます。
→職場定着率の向上、職場の満足度向上、知識・ノウハウの継承、社内コミュニケーションやネットワークの活発化、組織風土の改善、社員の能力向上、逸材発掘
【メンティ】
働く上でのビジョン明確化、無用な躊躇や不安の払拭、成長スピードアップ、仕事に対するモチベーション向上
→知識・ノウハウの吸収速度向上 、自立・自律、対人能力向上、社内コミュニケーションやネットワークの活発化、問題解決・能力向上、職場満足度向上、キャリアプラン、将来のビジョンの明確化
【メンター】
メンティを支援することで、自分自身の仕事や生き方の振り返り、対人コミュニケーションへの気付きや学び、更なる成長
→対人能力向上、指導・育成能力向上、社内コミュニケーション・ネットワークの活発化、知識・ノウハウの洗い出し、責任感の向上
■メンター制度の「表面的な」マイナス面:
・直属の先輩や上司との関係性
→斜めの関係で実施した場合に、第三者が関わることで直属の先輩や上司が得てない情報があることから、事前にメンター制度に対する社内周知、理解浸透を行っていなければ、組織内の関係性がギクシャクする可能性があります。
・メンター、メンティの工数増加
→時間的な拘束、レポートや振り返りの時間など時間的な工数が発生します。
・メンター、メンティのストレス増加の可能性
→メンター、メンティのマッチングを行っただけで、目的や運用方法の設定、ツール活用などを行わず、ペアの二人に自由に任せていると、メンタリング実施の意味や効果を感じられず、実施自体が双方のストレスになることがあります。
※表面的なマイナス面と記載してあるのは、きちんとした導入・運用を行っていないために発生するものです。経営が制度にコミットメントし、導入時にしっかりと準備・説明を行うこと、運用をサポートすることで、上記のマイナス面はカバーできます。
4. メンター制度がうまくいかない場合ってどんな時?

メンター制度を導入したものの、うまく機能させることができず、形骸化して一年で終了というケースが多々あります。
メンター制度は、メンターとメンティを組み合わせて面談を行う機会を提供するというシンプルな形なので、とりあえずやってみようとスタートしてしまいがちですが、斜めの関係だからこそ、準備と運用を丁寧に行わなければ、機能しないどころか逆効果になることもあります。
実際、導入したものの、実施されず形骸化した、期待する成果が出なかった、ということでメンター研修の実施や運用の相談を受けることが多々あります。
それは、目的であったり、組織のバックアップ体制であったり、メンターの接し方であったり、と必要な要素の何かが欠けているが故です。また、一年程度の短期間での明確なアウトプットや結果を求められうことで、一年やってみたけど費用対効果が分からないので、効果が出ないので中止、という判断になることもあります。
しかしながら、必要な要素を満たした上で、丁寧に運用継続することでメンティがいずれメンターとなり、育成文化が醸成され、組織の風土が変わり、といった具合に成果につなげている企業や団体も実際にあります。
実施する前の準備及び実施中のフォロー、実施後の振り返りを丁寧に回し、次年度につなげていくことが大事です。
■メンター制度の効果が出ないケース:
・進行の問題
・取組み姿勢の問題
・目的・テーマ・目標 設定の問題
・問題が発生しているにも関わらず、惰性で継続している
・関係性(遠慮、相性)
ほか
■メンター制度で起こりがちな失敗例:
・メンターが相手視点に立てない
・安心できる場であるはずが、プレッシャーの機会となっている
・直属の上司・先輩との関係性
ほか
コラム:メンター制度実施で、メンターが抱える悩みと対処法とは?
5.ピアメンタリング

ピア(peer)は仲間という意味で、言葉が指すとおり、1:1ではなく、共通のテーマを持つ複数人が定期的に集まり、互いの関心事や相談事を共有し、一緒に考えることで相互成長を図る仕組みです。
対等な関係の中で話し合う中で、定期的に振り返りを行うだけでなく、様々な価値観や考え方に触れることができることで、有益な話し合い、成長につながっていきます。
全員が、気負うことなくコミュニケーションを取れるという点で、4名前後が適正人数と言えます。
1名の振り返り・共有に対する各人からの感想共有やアドバイスを行う時間を15分~20分とし、通常各回が60分~80分となります。
特に決め事はありませんが、話す準備をせずその場で共有事項を考えるとなると、時間が無駄になるため、振り返りの共有準備を各人が事前に行っていることが必要です。また、そのグループで効果を最大化するために、「遠慮しない」「率直に言いたいことを言う」「承認する」など、グループ内でルールを設定しておくのも有効です。
<実施者の声>
・回を追うごとに、次の回が楽しみになっていくのを実感できた。
・自分にはない考え方や価値観に触れることができて勉強になる。自分の思考パターンに気付いた。
・毎週進捗、成長が自分で認識できることに加え、周囲から自分が想像していなかったコメントや意見をもらえることが励みであり役にたっている。モチベーションにつながる。
・参加者が回を追うごとに元気になっていっている。振り返りの内容と1週間毎のシートの密度が毎回成長していっている。
・振り返りシート作成にあたり、ダメだった点やできていない点を発見し、嫌々でも自分に向き合う一方で、気づきや学びをある意味強制的に探すため、ダメな一週間、何もない一週間の中にも前向きになれる点が発見でき、自己効力感や元気につながる。
・上司の言っていることに納得できず、行動に本気で取り組めなかったが、前回の会でメンバーからから色々意見をもらって考えてみた。すると、自分に悪い点もあるのでは?と思い至り、上司がそういうことを言う理由を自分なりに考えてみたところ、自分にも修正すべき点があった。(同じ失敗を繰り返していた)その後、「同じミスを繰り返さないように意識しています」と上司に共有したところ、関係性が改善した。
6.リバースメンター制度

メンター、メンティの関係は、メンターが年長者、メンティが年下というイメージが強いですが、必ずしもそうである必要はありません。
本来のメンター制度は、若手社員やターゲット社員が抱える課題や悩みを、経験豊かなメンターがサポートするものですが、最近では、その立場を逆転させたリバースメンター制度を導入する企業が出てきています。
例えば、若手社員が役員のメンターとなり、モバイル機やSNSの活用法などITスキルを学ぶサポートを行う、といった事例が取り上げられています。パソコンが登場した時が、そうであったように、年々新しいものが世の中にアウトプットされますが、若者は、それらに自然になじんでおり、年配の社員よりも長けていることが多いため、それを、教わるというのは、自然な流れでしょう。目的はITスキルを学ぶことですが、実際に導入した企業では、役員から「新たな考え方や常識に触れ、刺激につながった」といった評価の声も高かったようです。
最新の機器や技術に関わりません。自分にない知識やスキル、経験を持った人であれば、メンターと成り得ます。
当然、通常のメンタリングと同様に、双方の成長につながります。
唯一懸念があるとすれば、自分よりも若い人がメンターとなることをメンティとなる本人が受け入れられるかどうか、という点でしょう。それが無ければ、リバースメンターも形だけで全く意味も効果もでません。
反対に、双方が受け入れ、実際に運用し効果につなげることができる組織であれば、色んな人、様々な環境から学ぶことが出来る組織ということであり、成長の機会も増え、成長し続ける事が可能になります。
敢えて制度にする必要があるのか、とも言われそうですが、相互育成という文化を醸成するメッセージとしても有効です。
7.外部メンター

メンターは、会社や組織で実施する必要はありません。自分の人生やキャリアにおいて、悩んだ時は課題を抱えた時に、アドバイス、サポートしてくれる方、自分が信頼できる方がメンターと言えます。
例えば、ベンチャー企業の経営者の成長のために、経験豊富な経営者がメンターとなることもありますし、転職した人が、前職の上司や先輩にメンターとなってもらって相談することもあります。
会社や団体のメンター制度が斜めの関係で組まれる目的の一つに、利害関係のないところで、評価に関わらないので相談しやすい、素直に意見を受け止める、といったことがありますが、その観点からすれば外部メンターには、利害関係が全くないので、100%そのメリットを享受できます。
同じ組織でないので、本音で相談しやすいことはもちろん、メンターとしても組織の事情を酌量する必要がない分、本当に適切な意見を出せると言えるでしょう。
外部メンターを選ぶ際は、「信頼できること」「社会経験を積んでいること」「主観でなく客観で物事を捉えられること」を最低限の規準にし、後は、自分が話しやすいかどうかといった観点で判断するとよいでしょう。
コラム:メンター制度実施で、メンターが抱える悩みと対処法とは?
動画:課題解決事例「メンターの悩み解決相談会」
<その他メンター制度に関する情報、相談、自社導入>
【買い切り型、MP4動画「メンター研修」】
【メンター向けアンケート、メンティ向けアンケ―ト】
【メンター制度導入運用コンサルティング】
【コストをかけず自社で実施「メンター制度導入運用ツールセット」】
コラム【教育体系構築】一覧は こちら
一歩一歩着実に、教育体系を整え、育成課題の解決を図りたい企業様に
毎月定額、定例の顧問型支援 「教育体系コンシェルジュサービス」
その他お問い合わせは こちら

一律 1on1面談はもう古い!目的や成長ステージに合わせた面談制度とは
特に、テレワーク増加に伴い、オフィスで共に働く中で自然にコミュニケーションを取るということができなくなったことから、オンラインでの1on1面談を実施する企業も増えています。
しかしながら、あまりうまく機能していないという声も聞こえるようになってきました。その理由と対応法はどういったものがあるでしょうか。
1.1on1面談制度とは

まずは、1on1制度について確認しましょう。
【取り組み内容】
上司と部下、先輩と後輩が1対1で30分から1時間程度、定期的に面談を行う制度
目的に応じて期間を設定してもいいし、特に期間を定めなくても良い。企業によっては、同じ部門ではなく、全く関係ない人と実施しても良いとしているところもあり、目標に対する進捗管理や実務に対するアドバイス、支援から人間関係構築、悩み相談、業績アップなど実施目的も様々。
【効果】
・PDCAを回す仕組みで「経験学習」「パフォーマンス向上」に有効
・部下・後輩の気持ちやモチベーションの変化に気付きやすい。(いい面、悪い面)
・上司・部下、先輩・後輩間の信頼関係が強化される
・自分で考える癖づけができる
・上司や先輩の育成力向上
・個人の業績やパフォーマンスの向上
・離職率低下
2.更に効果的なものにするために、目的や相手の成長ステージで実施面談を変える

1on1面談制度を実施する企業は増えましたが、一方で形骸化や実施者によって頻度や成果が異なるという属人化が課題として聞かれるようになってきました。
その要因として、相手の知識やスキル、経験問わず一律で実施していることや目的が不明確なまま実施していることが挙げられます。
例えば、隔週で30分~1時間程度、実施という形式で制度を定めているとします。
しかし、知識・スキル・経験の浅い新人や若手と豊富な中堅社員では、頻度や内容に求めるものが異なります。新人や若手は、実務スキルがないため聞きたいことも多く、進捗管理、モチベーション維持のため、もっとやってほしいと思うことが多いですが、知識・スキル・経験豊富な中堅以上は、目的を明確にしておかなければ、単なる進捗管理やコミュニケーションでは特に必要ないと思い、形骸化しやすい、もしくは投資時間に対する効果は低くなります。
また、目的を定めていないがために、折角の1on1が目標に対する進捗確認や問題解決といった業務に関することのみになり、受ける側がむしろストレスを感じる機会にしかなっていないというケースもあります。
うちは、不満が上がっていないという組織がほとんどでしょうが、単に、他のやり方と比較していないからということに過ぎないかもしれません。
目的や相手の知識・スキル・経験といった成長ステージに応じた面談を取り入れることで、1on1面談を受ける側の納得度も高まり、会社側も要求する内容を変えることができるため、組織全体として効果的なものにつながります。
では、具体的にどういう面談形式があるか確認していきましょう。
3.Daily 1on1面談制度
知識・スキル・経験の浅いメンバーの実務スキル向上を中心とした頻度優先の1on1面談です。知識・スキル・経験が浅く、個別に聞きたいことや進捗管理の優先度が高いため、1on1の面談を短時間でもいいので頻度高く実施します。

■目的:実務スキル強化、モチベーション維持
■対象:新入社員~実務に関する経験の浅いメンバー
■実施頻度:毎日もしくは2日に一回
■期待効果:
「互恵性」「返報性」(上司や先輩が自分のために時間を割いてくれているという事実に応えたいという思い)がメンバーの本気の努力につながります。頻度高く確認を行うことで、行動目標に対してできていたことへの承認機会が増えることになり、メンバーの自己効力感を高め、モチベーションを高い状態で維持できます。
また、当日うまくいかなかったことを翌日改善して活かすといった短時間でのPDCAを繰り替えすことで、PDCAの効果を認識し癖付けにつながります。
<YouTubeで確認>
4.業績向上面談
個人の視点・視座拡大と組織成長に目的を絞って四半期に一度実施する1on1面談です。実務面、モチベーションから離れ、社外に対しての視点、組織に対しての視座を引き上げ、組織改善に結び付ける面談で、それぞれの階層毎に得られるものが異なるため、階層問わず実施します。
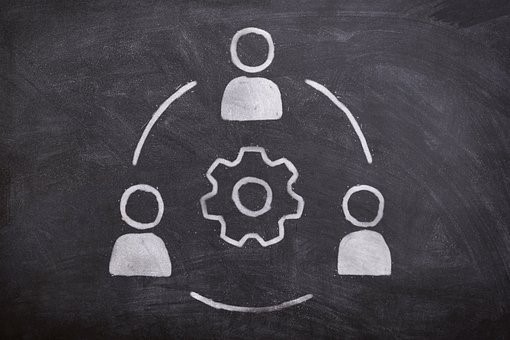
■目的:確実な行動変容、組織改革
■対象:不問
■実施頻度:四半期に一回
■期待効果:
視点・視座を個人から社外や組織に向けさせることで、意識が高まります。個々に眠る暗黙知としての現場での気付きや知見を形式知とし、組織に活かすことに有効なため、時代や環境の変化に即応ができます。また、現場から吸い上げた意見のため、組織で取り組むとなった場合に、当事者意識が高まり、確実な成長や変革を実現することが可能です。
面談を行う側も、普段、見ることができていない視点でコミュニケーションを行うことで、メンバー個々の視点や視座、普段どれだけ考えているかが明らかになり、逸材発掘にもつながります。
<YouTubeで確認>
→ 業績向上面談シート
5.相互育成を行うピア・メンタリング
主体的な成長、相互育成を目的として、同じような立場や職種で利害関係のない3,4名で定期的に実施する面談です。ふぃ
目的、目標・ゴール、取り組み内容、実施しての気づきや反省、今後について振り返るシートを用意し、面談前にそれぞれが記入。簡単に共有し、参加者からフィードバックを受けます。

■目的:従業員の自律成長、継続成長
■対象:中堅、自律人材
■実施頻度:週一回もしくは隔週一回
■期待効果:
取組みに対するフィードバックや相互アドバイスを複数名から定期的に受けることが、取り組みへの強制力にもなり、モチベーションにもつながります。自身では気づくことができない様々なヒントや内省につながり、実践、ブラッシュアップの効果が高まります。
上下関係や利害関係がないメンバーで実施することで、本音で率直なコミュニケーションを取ることができ、アドバイスも素直に受け止めることができます。
6.書籍からのPDCAによるリアルケーススタディ
自走型組織の構築を目的として、4,5名で実施する面談です。自ら読んだ書籍から設定したテーマを実務や組織で実践し、結果と今後どうするかをまとめて共有します。

■目的:自ら学び、試し、改善する組織づくり
■対象:不問
■実施頻度:四半期に1回もしくは半年に一回
■期待効果:
研修といった与えられた機会ではなく、自ら学んだことを実務に活かし、その結果をふまえてブラッシュアップ、PDCAサイクルを回していく自律成長のトレーニングとなります。
また、同階層や同職種で同じ書籍を読み、取り組み結果と改善案を共有し合うことで、自社におけるリアルケーススタディとなり、研修実施と同等もしくはそれ以上の効果につなげることが可能です。
7.ガス抜きから組織改善まで幅広く使えるオープンドア
管理職や上司と自由に話せる機会を提供する面談です。
管理職、上司は、日程、時間、場所をメンバーに共有し、設定した時間は誰かが来る来ない関わらず会議室(もしくはオンラインで)で待ちます。メンバーは一人で行ってもいいし、複数で行っても構いません。メンバーは何を話してもいいし、管理職、上司は、原則として聞くのみ、求められればアドバイスなどを行うというルールで実施します。

■目的:ガス抜き、組織への提言、チーム力向上
■対象:不問
■実施頻度:隔週に一回もしくは月一回
■期待効果:
管理職や上司が気づいていない様々なことを吸い上げることができます。挙がってくる内容に耳を傾け、必要に応じて解決していくことで、信頼関係強化、チーム力強化、組織改善につながります。
動画で学ぶ「部下後輩の成長を促進する育成コミュニケーションスキル動画」は こちら
コラム【教育体系構築】一覧は こちら
一歩一歩着実に、教育体系を整え、育成課題の解決を図りたい企業様に
毎月定額、定例の顧問型支援 「教育体系コンシェルジュサービス」
その他お問い合わせは こちら

自社で、自部門ですぐできる行動変容、組織成長につながる具体的方法
お金をかけずに、定例で実践できて、確実な行動変容、組織成長につながる育成方法をご存知ですか?
1.階層単位から職種、部門単位で実施可能な育成方法
研修を実施したいが、外部に依頼する予算がない。
実務、実績、行動変容につながらない研修なら実施する意味がない。
そんなお考えの場合に、自社で、自部門ですぐできて、工数、コストをかけることなく、行動変容、効果につながる育成方法をご紹介します。
階層別、職種別、部門別問わず、行動変容、効果につながります。
2.具体的な方法とは
一人数千円で手軽に実施できる取り組みです。
研修形式で、ノウハウ、ドゥハウを学ぶINPUT型の研修だと、様々なワークや事例が用意されていたとしても、講師対自分という構図になるため、過去の成功体験が豊富であればあるほど、業務や職務が特殊であればあるほど、自分の場合はこうだ、この仕事はこうだ、うちの部門はこうだ、という結論になりがちです。
そうならないように、講師対自分ではなく自分対自分、自分対同列の受講者という、一人ひとりが主役の勉強会、報告会にします。動機づけ理論である自己決定理論で自律性(自己の行動を自分自身で決めることに対する欲求)によって内発的動機付けがなされると提唱されていますが、人は、自ら気付いたこと、自分で決めたことに対しては、行動につながりやすくなります。
ただし、ただ自分で目標設定を行って、実践、共有を行っても、参加者の共通概念や認識がないため、自分にとっては役立ちますが、他の参加者にとっては、あまり意味がないものとなります。
そこで、書籍を活用します。参加者が同じ課題図書を読み、その中から自身が気になった内容を取り上げ、実践計画を立て実践、その結果と結果をふまえて今度どうするかという勉強会兼報告会を実施。
PDCAの意義を認識するとともに、「自ら学び、試し、次につなげる」という自律成長のクセ付けにもつながるトレーニングとなります。
3.実施フロー 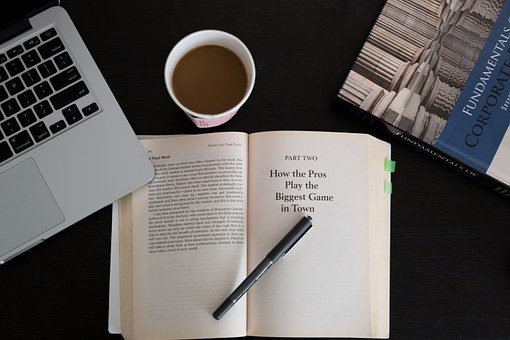
【パターン1:報告会】
書籍を読んで、気に内容から実践計画を立て実践、その結果と今後のアクションをまとめた内容を報告し合う機会を設け、互いにブラッシュアップを行います。報告会が実践に対する強制力となります。また、同じ書籍を読んでいるため、他参加者の取り組みも、自分では取り組まなかったアクションについて、どういう結果につながるのかケーススタディとして自身の糧となります。
<実施フロー>
STEP1.課題図書決定
STEP2.各自読む
STEP3.書籍に書かれている内容で気になったテーマに関して具体的アクションを設定し、実践(3か月から半年)
STEP4.報告会にて設定テーマ、実践アクション、結果、変化、今後について共有、感想・相互アドバイス
【パターン2:勉強会】
報告会から更にレベルを引き上げた取り組みです。
書籍を読んで、気になるテーマを設定、テーマの要旨説明とどうすればそれを実現できるかを一人ひとりが講師となり、他受講者にプレゼンテーションを実施。その場でブラッシュアップを行い、その勉強会をふまえて、各自アクションプランを立て、実践。後は報告会と同様に、実践結果、変化、今後について共有、感想・相互アドバイスを実施します。
ラーニングピラミッドという考え方で提唱されているように、人が一番学ぶのは誰かに「教える」というアクションを行う時です。人に教えるためには、本当の意味で理解しておく必要があるからです。どうすれば、より伝わるか理解できるか、事例を考えたり、簡単なワークを考えたりする中で、更に理解は深まります。
<実施フロー>
STEP1.課題図書決定
STEP2.各自読む
STEP3.勉強会:一人ひとりが講師となりプレゼンテーション
プレゼンテーション内容
・概要説明:書籍の中の対象部分の要旨説明
・講師として教える:ここがポイント、こう考えよう、取り組もうと伝える
・質疑応答、相互ブラッシュアップ
STEP4. 勉強会内容をふまえて各自取り組むテーマとアクションプランを設定し実践(3か月から半年)
STEP5.報告会にて設定テーマ、実践アクション、結果、今後について共有、感想・相互アドバイス
※勉強会でプレゼンテーションを行う内容は、会社側で割り当て指定してもいいし本人が自由に選択しても良い
4.実施効果
報告会、勉強会の取り組みは、支援先で実施をして大きな変化・成果につなげることができています。取り組みの中で分かった報告会、勉強会の効果をご紹介します。
・言語化、見える化することでアクション、PDCAにつなげやすくなる
・自分で決めたことなので、取り組みに対して当事者意識を持って実施できる
・報告会、勉強会の存在が強制力となることで、書籍の読み方、取り組み方の本気度が高まる
・対象者全員が同じ本を読むことで、共通認識・共通言語でコミュニケーションができるようになる
・同じ書籍を読んでいること、実践でうまくいった、いかなかったの実体験により、質疑応答や意見交換が活発に行われ、それ自体が気づきやヒントにつながる
・自社の事例なので、取り組みも結果も納得感が高い。リアルケーススタディとして参考になる。
通常の研修では到達できない実務、実績、行動変容の実現につながります。
5.お勧め書籍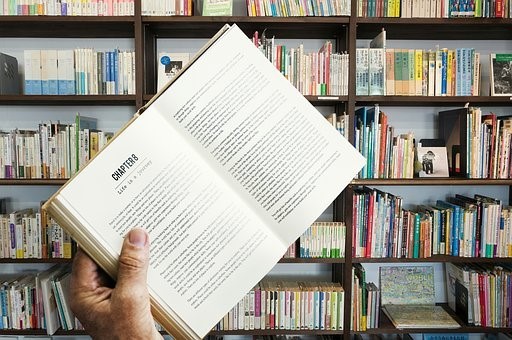
本取り組みを行うにあたってのお勧め書籍をご紹介します。
【当事者意識、成長意欲の醸成】
■職場が生きる 人が育つ 「経験学習」入門
他人から言われても、当事者意識や成長意欲にはつながりません。成長する人材が何故成長するのか、「学ぶ力」を身に着け、自身につながる仕組みがわかりやすく理解できます。管理職が読んで指導するのにも向いていますが、自ら読むことで、理解が深まり、素直に受け入れるようになるので、報告会や勉強会の取り組みにお勧めです。
<目次>
序章 経験から学べる人、学べない人
第1章 成長とは何か
第2章 経験から学ぶ
第3章 経験から学ぶための三つの力
第4章 「思い」と「つながり」
第5章 学ぶ力を育てるOJT
第6章 学ぶ力を高めるツール
■シェアド・リーダーシップ-チーム全員の影響力が職場を強くする
職場の誰もが互いに得意なことを認知し、必要なときにリーダーシップを発揮する状態「シェアド・リーダーシップ」について書書かれている本です。今の世の中にマッチしたリーダーシップと言え、当事者意識、モチベーション、一体感、職務満足、業績向上につながっていく仕組みや効果を分かりやすく解説しています。
<目次>
第1部 効果的なリーダーシップを発揮するために
第2部 シェアド・リーダーシップについて
第3部 職場をシェアド・リーダーシップにするために
【管理職向け】
■HIGH OUTPUT MANAGEMENT
管理職、マネジメントに関する書籍は様々読んできましたが、本質がおさえられていて、一番納得感の高かった本です。マネジメントの本質的な役割、組織としての生産性をあげるための取り組みが、シンプルに体系立てて整理されており、事例も豊富です。管理職であれば一度は読んでおきたい書籍です。
<目次>
第1部 朝食工場ー生産の基本原理
第2部 経営管理はチーム・ゲームである
第3部 チームの中のチーム
第4部 選手たち
■「空気」で人を動かす
人を動かす、組織を変えるために場の空気に焦点をあて、その変革を行うことで人と組織の成長を促すメソッドについて書かれた書籍。誰もがなんとなく感じていることを言語化することで、現状把握と改善方法を具体的に行えるように書かれた書籍です。
<目次>
第一章:チームの「空気」を現状分析せよ
第二章:「悪い空気」の元凶を解明せよ
第三章:チームの「空気革命」を遂行せよ
第四章:「空気」を「流れ」に変えよ
第五章:「空気革命」の成功者から学べ
【経営幹部・上級管理職向け】
■新しい経営学
仕事に使える「経営視点」が身につく画期的入門書と帯に書かれているとおり、学問が実際の企業事例によって分かりやすく理解できるため自社に置き換えて実施するには、とても役立つ書籍です。
<目次>
1章:ターゲット:誰を狙う
2章:バリュー:提供価値は何?
3章:ケイパビリティ:どうやって価値を提供する?
4章:収益モデル:どうお金を回す?
5章:あと3つ:事業目標、共通言語、IT/AI
補章:ミクロ経済学基礎と経営戦略史
その他、職種別であれば職種専門書籍、部門別であればチームワークや方向性決定、戦略戦術に関する書籍を選んで実施するのも一つです。
★取組案内資料、ワークシート、実施ガイド付き 課題図書実践&報告会の実施ツールを購入できます。
【ガイド付き版】行動変容、組織成長を実現する 課題図書実践&報告会の詳細確認は こちら
コラム【教育体系構築】一覧は こちら
一歩一歩着実に、教育体系を整え、育成課題の解決を図りたい企業様に
毎月定額、定例の顧問型支援 「教育体系コンシェルジュサービス」
その他お問い合わせは こちら